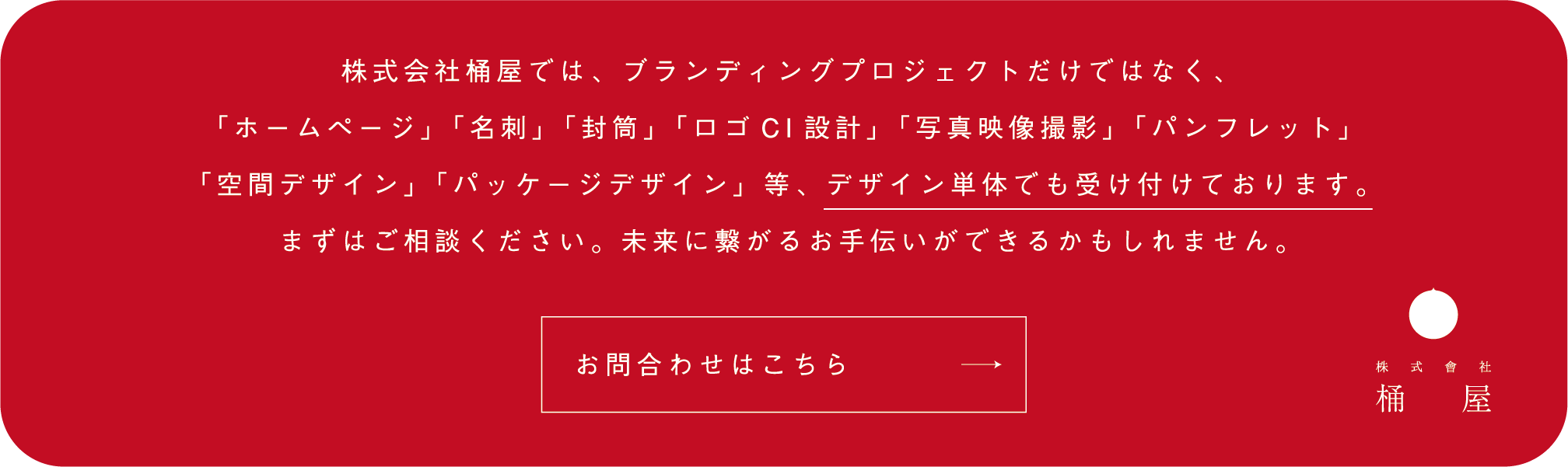お土産メーカーブランディングデザイン
お土産メーカーブランディング成功事例

今回のミッション/ご依頼の経緯
1986年の創業以来、毎年多くのお土産を生み出しているツジセイ製菓株式会社様。
水族館・動物園・テーマパークや観光名所、駅、空港、サービスエリアなどに置いてあるお土産やご当地キャラクター商品などを幅広く手掛け、企画・提案から、商品・パッケージの加工までを一貫して行っておられます。
新社長就任と共に、今まで取り組んできたことを一度棚卸して整理整頓し、
「会社のイメージに合ったデザインを施して欲しい 」という代表の田中社長様からのご依頼でした。
また食品表示法の変更による会社名の露出度のアップ、既存顧客へのイメージ向上、新規顧客への訴求力向上、
求職者の絶対数アップ、地元香川で愛され、永続するお土産企業に成るべく、リブランディングプロジェクトがスタートしました。

贈る感動を製造する「お菓子(おかし)な会社」
お土産とは、生きていく中で必ずしも必要ではありません。
しかし人と人とを繋ぐ大事な役割を担っています。
お土産を選んでいる時、相手のことを考えながら、お土産を選びます。
お土産を待っている時、帰ってくる喜びとお土産が待ち遠しくなります。
お土産を源として、想いが結び繋がる。
人と人が結び繋がる。お土産にはそんな不思議な力があります。
日本中のたくさんの人たちを笑顔にし、贈る楽しみ、もらう喜びを伝える
商品つくりを目指し、お菓子の持つワクワクやハッピーなイメージをそのままに
贈る感動を製造する「お菓子(おかし)な会社」。
こそがツジセイ製菓株式会社様の全ての根本。
真面目過ぎても面白くない。
老舗の饅頭屋の重厚感のある雰囲気でもない。
巫山戯過ぎても温度感からずれて来る。
要はどの塩梅でバランスを保つか。絶妙な塩加減が必要なのです。
その塩梅を理解しアウトプットするかという点が
リブランディングプロジェクトで重要なポイントです。
デザインのプロセスと解剖



ロゴマークとは何か?
僕たちはお守りだと捉えます。
経営者や企業の考え、歴史、今の現状、未来に進むべき方向を、1つのマークに変化させます。
いつ見ても誇りに感じ、何かあればそのロゴマークを見れば原点に立ち戻れる「お守り」なのです。
ブランディングのヒアリング途中に「ロゴの意味を説明してください」だけではなく、
「ロゴマークを書いて下さい」と参加メンバー全員に突然投げかけます。
色はなんとなく覚えていても、90%以上の方は書けません。
戦国時代の武将は自分の家紋を旗に高らかと掲げ、兜に付け、敵陣に乗り込んでいきます。
戦に負けたとき、本当の屈辱は自分たちの誇りにしている旗を足で踏まれ燃やされることです。
だからこそ丁寧に作り込むべきはロゴマークなのです。
ネットで注文1週間で本当のロゴは出来ません。
会社の中心にあるロゴマークの意味や成り立ち、形状を深く知ることで会社の思想が理解できます。
社員方々が意味を理解し、ロゴマークも書けるような会社は間違いなく成長します。


アップル・スターバックス、国内では明治・花王。
挙げるとキリがありませんが、多くの企業が成長とともにロゴをマイナーチェンジします。
大きく変わるのではなく、マイナーチェンジ。
時代の変化とともにデザインの耐久性が劣化し、変えざるを得ない場合もありますし、
何か新しいメッセージ性を付け加えたい場合もあります。
今回の場合は前述の両方で、今まで支えてくれたロゴを大切にしながらも
これからの新しい未来を支えてくれる新しいロゴ。
外見こそはガラッと変化はないかもしれないが内面に大きな変化がある。
外見の変化も当然大切ですが、内面のコンセプトの見直しも同じくらい重要。
是生滅法。変化しないものはない以上、変化するのは当然の摂理である。













エッジの効いたデザインにエッジの効いたオーバル。
贈る感動を製造する「お菓子(おかし)な会社」というコンセプトに恥じぬ名刺。















ブランディングプロジェクト開始後、欠かせぬ年間行事となりました。
筆文字に謹賀新年。その横にはコピペで取ってきたようなそこら中で見かける文章。
これでは埋もれて至極当然。埋もれるにも理由があります。
それらと対極にあるツジセイ様の年賀状はお土産/お菓子業界で噂になっていたようです。
毎年、毎年コンセプトを練り、両社長様も撮影にはノリノリで取り組んで頂きました。
年賀状のチカラを舐めてはいけません。年賀状一つでもブランディングは成立するのです。
年賀状はブランディングで大切な要素です。

































コーポレートサイト
http://tsujisei.co.jp/
採用サイト
http://tsujisei.co.jp/recruit/







裏面のクラフト紙質をパイ生地と見立て、
表のホワイトクラフトはホワイトチョコをコーティングしたパイのようなお菓子な封筒。
ツジセイの主人公でもある「パイ助」が覗き込んで欲しくない封筒から
逆に覗き込むというコンセプトで
今日も郵便局員さんに笑顔で運んでいただきます。





求職者がなぜ働きたいと感じるか?
それを可視化(見える化)しないと求職者は集まりません。
本来は非常にシンプルなのです。
ブランディング後求職者は数倍に増えました。
小手先の採用サイトだけを作っても求職者は増えません。
もしあなたの人生を考えている時にそんな小手先感の感じる会社に行きたいでしょうか?
答えは其れです。












桶屋の写真講座では最短距離で上手くなる方法のみをお伝えします。
書店に並んでいるような本の知識ではなく、
本当に上手くなる方法を。
カメラは最初iPhoneで十分です。
iPhoneで上手く撮れないのに何十万も出して一眼を買っても上手く撮れません。
写真は会社の大切な資産です。
写真一枚で会社の伝えるイメージが大きく変わるのです。
いつの時代も変わらぬ普遍ですね。
3年という時間を共にし、ブランディングの礎をつくりあげる










振り返ると初めてお会いしたのが2017年9月。
その時のお話を今でも鮮明に覚えており、
社員の皆さんの働きやすい環境や、普段行っていることをきちんと世の中の人に知ってもらいたい
から写真やデザインで見える化したい。とご相談いただきました。
「可視化する」という作業はどれだけ一つの事に真剣に向き合えるか、
そして中途半端で終わらず最後まで良い結論が出るまで忍耐強く出来るか。
この忍耐が非常に難しく、「これでいいや」にしてしまうと、それなりになります。
会社の一番深い部分をプロジェクトチーム全体で話し合って1つの結論が出ました。
このブランディングという仕事は、本当に言いにくいことや触れたら爆発しそうなことに
時には優しくタッチし、時にはガッと手掴みしなければならない。
内心はゴメンナサイという気持ちがありますが、一度爆発を起こすコトでより良い再生が生まれます。
リリース時には登壇し、1時間ほど全社員さんの前で今までやってきたこと、
これから取り組むことの話をさせていただきました。
実はブランディングするという事は本当は楽しい部分がいっぱいあります。
難しい顔して悩む時期を通り過ぎたら、メンバーで笑いながら前に進んでいくことが大事だと思います。
そう考えるとブランディングが社内で浸透していない会社の原因の一つは
難しい顔して、「ブランディングとはこうである」みたいなことばっかりやっているのかもしれませんね。
ブランディングを楽しむこと。これに尽きます。



本社所在地:〒761-1704 香川県高松市香川町川内原1591-1
創業:1986年6月
従業員数:110名
http://tsujisei.co.jp/
【お土産ブランディングプロジェクト】
CI構築・ロゴマーク・ホームページ・写真撮影・名刺・会社パンフレット・商品パンフレット・お土産パッケージデザイン・年賀状デザイン・封筒デザイン・空間ディレクションデザイン・就職フェアブースデザイン